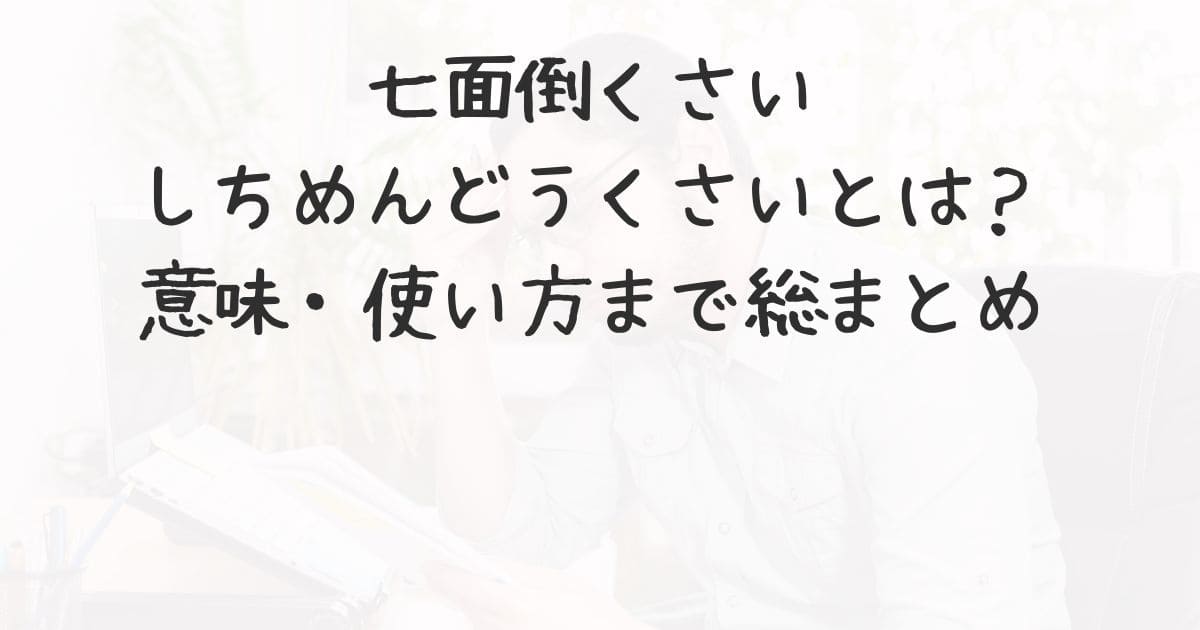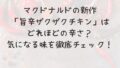「七面倒くさい(しちめんどうくさい)」という言葉、最近のニュースで耳にして気になった方も多いのではないでしょうか?
普段あまり使わないこの言葉には、実は深い意味が込められています。
本記事では、「七面倒くさい」の意味や使い方はもちろん、SNSでの反応まで、やさしい言葉で丁寧に解説していきます。
【まずはここから】「七面倒くさい」の意味とは?

「七面倒くさい」とは、簡単に言えば「いくつもの面倒なことが重なっていて、本当に手間がかかる」「手続きや対応に時間も労力も取られてしまう」といったニュアンスを持つ言葉です。
この言葉は、単に「面倒くさい」と言うよりも、さらに状況の複雑さや厄介さを強く印象づける表現です。
「一つの問題だけではなく、二重三重に手間が発生している」というような場面でよく使われます。
また、この表現には少し昔ながらの響きがあり、現代ではあまり日常的には聞かれないものの、重みのある言い方として知っておくと便利です。
特に「思わずため息が出てしまうような、何から手をつけたらよいかわからない」と感じるような状況にぴったりです。
例文でイメージしてみましょう
- 「この役所の申請、書類が多すぎて七面倒くさくて嫌になるね」
- 「家庭の事情と仕事のスケジュール調整が重なって、まさに七面倒くさい状態だよ」
- 「彼の話は毎回まわりくどくて、聞いているだけで七面倒くさく感じる」
少し古風で大人びた印象のある表現ですが、その分、状況をより的確に表すことができる便利な言葉でもあります。
なぜ「七面倒」なの?言葉の由来と背景を探る

「七面倒くさい」という表現には、「七(しち)」という数字が含まれていますよね。
この「七」というのは、単なる数ではなく、「たくさんの」や「いくつもある」という意味合いを持つ、象徴的な数字として使われています。
つまり、「七面倒くさい」とは、「一つや二つではなく、あらゆる方向から手間や厄介ごとが押し寄せてきているような感覚」を表す言葉なのです。
この言い回しは、昔から日常会話だけでなく、文芸作品や落語、演説などのさまざまな場面でも使われてきました。
日本語においては、特定の数字に象徴的な意味を込めることがあり、「七」はその中でも特に頻出するもののひとつです。
似たような表現
- 七転八倒(しちてんばっとう):何度も苦しみながらも、必死で立ち上がろうとする様子
- 七難八苦(しちなんはっく):人生におけるありとあらゆる困難や苦しみを表現した言葉
- 七変化(しちへんげ):次々と変化すること、多彩さを表す表現
このように、「七」という数字は、日本語では“多くの”“複雑な”“繰り返される”といった意味合いを象徴する数字として、さまざまな表現に登場しています。「七面倒くさい」という言葉にも、こうした背景が色濃く反映されているのです。
「七面倒くさい」は方言?全国的に使われている?

「七面倒くさい」という表現は、特定の地域に限られた方言ではなく、日本全国で広く知られている標準的な日本語表現のひとつです。
昔から文書や会話の中で使われてきたため、世代や場所にかかわらず意味が伝わりやすいという特徴があります。
とはいえ、最近ではこの言葉を日常的に使う機会が減ってきているようで、特に若い世代の間では聞きなれないと感じる人も多いようです。
そのため、「七面倒くさい」という言い回しに触れると、どこか懐かしさや古風な印象を抱く方も少なくありません。
SNSでの使用状況
実際にX(旧Twitter)などのSNSでこの言葉を検索してみると、40代以上の大人のユーザーによる投稿が多く確認できます。
たとえば「子どもの頃、母によく“七面倒くさいからやめなさい”って言われた」など、思い出や昔話と一緒に語られることも多いです。
また、日常の出来事をユーモアを交えて表現する際にも「七面倒くさい」という言葉が使われており、共感を呼ぶ投稿として反響を集めていることもあります。
そのため、懐かしいながらも現代において一定の需要と共感性を持つ表現として、今も生き続けていることがわかります。
「七面倒くさい」は使っても大丈夫?現代での印象と注意点

「七面倒くさい」という言葉は、親しい友人や家族との会話では、ちょっとした冗談や共感の気持ちを込めて使える便利な表現です。
たとえば、「それって七面倒くさいよね〜」と軽く口にすることで、相手の大変さに寄り添ったり、場の雰囲気を和ませたりすることもできます。
ただしこの言葉は、通常の「面倒くさい」よりもさらに強調された印象を持つため、使う相手やシチュエーションによっては少しきつく響いてしまうこともあるので注意が必要です。
避けたほうがよい場面
- ビジネスの場面(上司や取引先との会話など)では不適切に感じられる可能性があります。丁寧な言葉づかいが求められる場では、より中立的な表現に置き換えた方が無難です。
- 相手の行動や提案を否定する文脈で使うと、「批判している」「不満を持っている」と誤解される恐れがあります。
- SNSやオンライン投稿など、文脈が見えにくい場所で使う場合にも注意が必要です。言葉だけが独り歩きしてしまい、意図とは異なる意味で伝わることもあります。
このように、「七面倒くさい」は状況や相手との関係性をよく見極めて使う必要があります。
言葉のチョイスひとつで印象が変わる時代だからこそ、丁寧さと思いやりを持ったコミュニケーションを心がけたいですね。
似たような言葉・言い換え表現で印象を和らげよう

「七面倒くさい」が少し強すぎる、または相手にきつく聞こえてしまいそうだな…という場面では、やわらかい言い換え表現を使うのがおすすめです。
日本語には、似た意味を持ちながらも、より穏やかな響きを持つ言葉がたくさんあります。相手に配慮しながら自分の気持ちを伝えるためにも、こうした表現を知っておくと便利です。
使いやすい言い換え表現例
- 煩雑(はんざつ):細かくて複雑で、処理が面倒なさまを表します。「煩雑な手続き」など、書き言葉としてもよく使われます。
- ややこしい:物事が入り組んでいて理解しづらい状況に使われます。「ややこしい人間関係」など、日常会話でも自然に使えます。
- 手間がかかる:作業や準備などに時間や労力を要することを指します。「この料理は少し手間がかかるけど美味しいよ」といった前向きな表現としても使えます。
- 複雑:構成や仕組みが入り組んでいる様子を指し、冷静に状況を説明したいときに便利です。
- 気を使う:心理的な負担を表現したいときに使える表現です。「あの人との会話はちょっと気を使うよね」など、場面に応じて選べます。
このように、表現を少し変えるだけで、相手に与える印象を柔らかくすることができます。
特に仕事の場や目上の人との会話では、こうした言葉選びが信頼感や丁寧さにつながります。
相手の気持ちを思いやった言葉遣いは、よりスムーズで心地よいコミュニケーションにもつながります。
実際に使ってみた!「七面倒くさい」な出来事エピソード集

ここでは、身近で「これは七面倒くさい…!」と感じた出来事をいくつかご紹介します。
誰にでもある“ちょっとした面倒”のなかに、「ああ、これがまさに七面倒くさいってことか!」と思える瞬間がありますよね。
- 行政手続きが複雑で、必要書類を何度も確認し、記入ミスで書き直し、さらに窓口で再提出を求められた。
- オンラインのパスワード再設定が何重にもなっており、本人確認メールのリンクが期限切れ、結局サポートに連絡する羽目に。
- 家族全員の予定を調整して旅行を計画したら、予約変更や連絡事項が次々に発生し、当日を迎える頃にはすでに疲れていた。
- 保険や携帯プランの見直しをしようとしたら、手続きが複雑すぎて放置しがちに。
こうした出来事は、日々の中で誰にでも起こり得るもの。
共感を呼ぶ「七面倒くさい」体験は、ちょっと笑えるけど、意外と奥が深いんです。
「あるある!」と感じた方も多いのではないでしょうか?
❓よくある質問(FAQ)

Q1:「七面倒くさい」はビジネスで使っていい?
A: 少し砕けた印象があるため、ビジネスの場では避けた方が無難です。
特に上司や取引先とのやり取りでは、「煩雑」「複雑」「調整が多い」など、もう少し丁寧な言葉に置き換えると好印象を与えられます。
カジュアルな社内コミュニケーションでは通じることもありますが、相手との距離感に気をつけましょう。
Q2:「七面倒くさい」は方言?
A: 方言ではなく、全国的に通用する日本語表現です。
ただし、若い世代の間ではあまり使われなくなってきており、やや古風な響きを感じる人もいるようです。
年齢層や使う場面によって、伝わり方に差が出る可能性もあります。
Q3:他に似た意味の言葉は?
A: 「ややこしい」「手間がかかる」「複雑」「煩雑」「込み入っている」などがあります。
これらの表現は、それぞれ少しずつ意味や印象が異なるため、伝えたい内容や相手との関係性に応じて、適切な言い回しを選ぶのがおすすめです。
まとめ|「七面倒くさい」は奥深い!でも言葉選びは丁寧に
「七面倒くさい」という言葉は、ただの「面倒くさい」よりも強い印象を与える表現です。
使い方を間違えると誤解を招くこともあるため、相手や場面に応じて丁寧な表現を心がけたいですね。
言葉の力を味方につけて、やさしく・わかりやすく気持ちを伝えていきましょう。