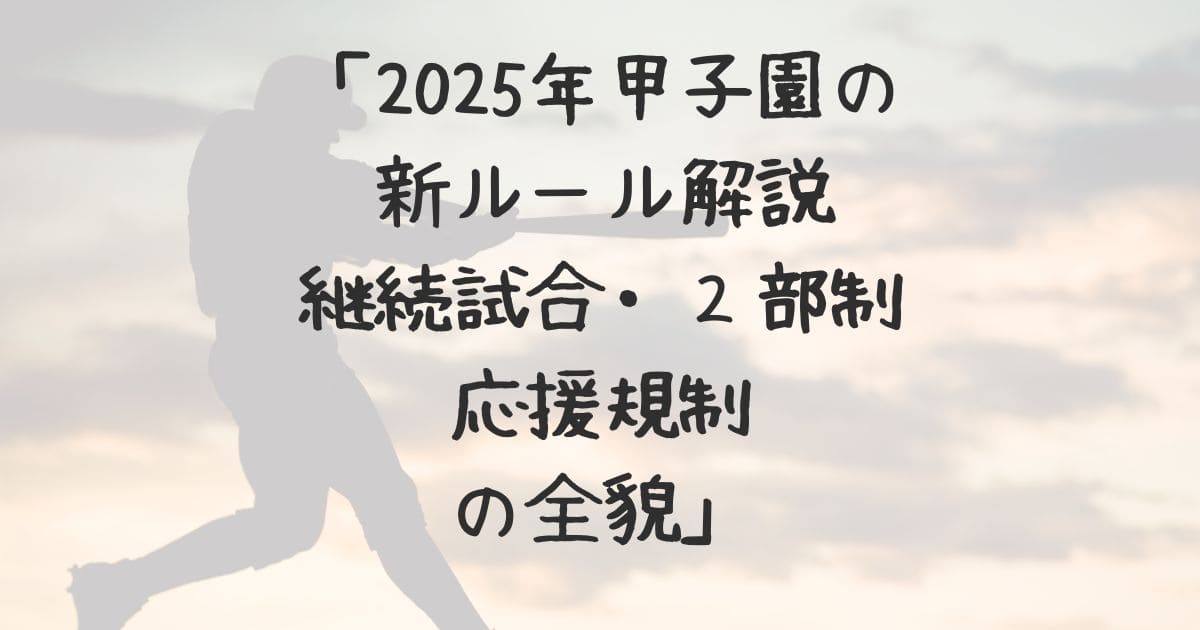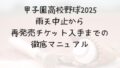今年の夏、甲子園球場では高校野球の運営に大きな変化が訪れました。
酷暑が続く中、選手の健康と大会運営の両面を考慮して、新たに「継続試合」と「朝夕2部制」が同時に導入されたのです。
これまでの降雨による打ち切りルールを刷新し、選手の努力を正しく記録に残すとともに、投手の球数制限との整合性を図ることで、より公平で安全な試合環境を整える狙いがあります。
2025年夏、甲子園が迎えた新たなステージ

ここ数年、真夏の気温上昇は年々厳しさを増し、熱中症の危険が高まっています。
こうした状況を踏まえ、主催者は大会第1日から第6日までの試合を「午前の部」と「夕方の部」に分ける2部制を採用しました。
この形式では、午後1時30分以降は午前の第2試合が新しいイニングに入れず、さらに午後10時を過ぎると夕方の第4試合も同様に終了となり、試合は翌日以降に持ち越されます。
この時間制限が設けられたことで、たとえ雨が降らなくても試合が途中で終了し、翌日に再開される「継続試合」が発生しやすくなったのです。
継続試合とは? ――従来ルールを覆す新制度

導入の背景
継続試合は、2022年春の選抜大会から導入され、夏の選手権大会でも採用されるようになりました。
その最大の目的は、これまでの降雨コールドやノーゲームといった制度で生じていた不公平感をなくすことにあります。
以前のルールでは、7回まで進行していればリードしていたチームがそのまま勝利と判定される一方、7回に満たない状態で中止となると試合自体がなかったことにされ、翌日以降に再試合が行われていました。
この場合、投手が投げた球数や打者の記録はすべて無効となり、選手たちの努力が報われないケースが多かったのです。
2021年夏、大阪桐蔭対東海大菅生戦が転機に
このルール見直しのきっかけとなったのが、2021年夏の大阪桐蔭と東海大菅生の一戦です。
試合は8回表、1死一・二塁という緊迫した場面で降雨コールドが宣告されました。
反撃のチャンスを残していた東海大菅生は悔しさをにじませ、多くのファンからも「選手の記録がすべて消えるのは不当だ」と疑問の声が上がりました。
この出来事が契機となり、試合を中断した時点から翌日に再開する現在の継続試合制度が形づくられたのです。
選手を守る仕組みとしての効果
継続試合の導入は、投手の球数制限とも相性が良いとされています。
現在、高校野球では1人の投手につき1週間で500球以内という制限が設けられています。
従来のノーゲーム方式では、再試合が発生すると投手が二度も多くの球数を投げることになり、肩への負担が増大していました。
しかし継続試合では、投球数は中断時の記録を引き継ぐため、無駄な消耗を防ぐことができます。
このように、「継続試合」+「時間制限」という新たな仕組みは、選手の安全と試合の公平性を両立する画期的な制度として注目されているのです。
2部制がもたらす「時間のパズル」

今年の甲子園では、猛暑対策の一環として「朝夕2部制」が大幅に拡大され、試合運営の仕組みが大きく変化しました。
これにより、設定された時間を過ぎた場合は試合を翌日に持ち越す「継続試合」が発生しやすくなっています。
具体的には、午前の第2試合は13時30分を過ぎると新しいイニングに入れず、13時45分になると強制的に打ち切りとなります。
さらに夕方の第4試合も22時が終了のリミットとして設けられ、これら二つの時間制限が、天候とは関係なく試合を翌日に分割するきっかけになっているのです。
1-1 試合開始が遅れると即タイムオーバー
1日に4試合が組まれるスケジュールは「8:00」「10:30」「16:15」「18:45」と決められています。
しかし、延長戦やリプレイ検証などが長引けば、後の試合が次々と遅れてしまいます。
特に夕方の第4試合は、開始時間が18:45でも投手戦や継投合戦が重なれば試合時間が3時間半を超えることもあり、22時の制限がすぐ目の前に迫ります。
結果として、高校生の大会でありながら、プロ野球さながらのナイトゲームが発生するケースも出てきています。
実例:開星対宮崎商(1回戦)
この試合は延長タイブレークの末、10回にサヨナラ犠牲フライで決着しましたが、試合終了は13時33分。
あと2分遅ければ甲子園史上初となる「時間超過による継続試合」になるところでした。
1-2 打ち切り後は必ず翌日以降へ
夕方に中断したからといって、その日のうちに試合が再開されることはありません。
続きは必ず翌日の空き時間に組み込まれます。
そのため、4試合開催日のうち1試合でも継続試合が発生すると、翌日以降の全試合スケジュールが押し込み式でずれ込む可能性があります。
この“ドミノ式の影響”は、大会全体の進行に大きな負担となります。
2.運営側が仕掛ける「空白デイ」という調整弁

主催者はこうしたリスクを見越し、大会第4日(8月8日)を午前2試合のみに設定し、第7日と第8日も3試合編成としました。
これにより、継続試合が発生してもこの空き時間を利用して試合を組み込み、全体の遅延を吸収できる仕組みを作っています。
ただし、この余裕にも限界があります。雨天順延が重なれば、準々決勝以降の日程や休養日が圧迫される可能性が残っています。
観客にとっては観戦計画が崩れるリスクが高まり、アルプス応援団や地方からの観戦者の交通・宿泊手配にも影響が及ぶでしょう。
3.球児たちが直面する「体内時計」との戦い

3-1 早朝集合と深夜解散の繰り返し
朝8時からの試合が組まれた場合、選手は6時前に球場入りする必要があります。
逆に第4試合が22時を過ぎれば、宿舎に戻るのは深夜0時を回ります。
さらに翌日にまた朝試合が組まれれば、睡眠時間は3〜4時間程度しか確保できません。
長期滞在が前提の甲子園では、この生活リズムの乱れが選手の体力に大きな影響を与えます。
3-2 投手の肩を守るか、それとも乱すか
投球数制限は1人あたり1週間500球以内と定められています。
しかし、継続試合によって登板が2日連続となると、投手の調整感覚が狂いやすくなります。
投球数自体は通算で管理されるものの、肩を温める回数が増えることで疲労は蓄積しやすく、故障のリスクも上がります。
医科学委員会は現在、これらのデータを分析し、今後の追加ガイドライン策定を検討しています。
4.継続試合を巡る賛否両論

メリット
-
不公平感が強かった降雨コールド・ノーゲームを解消し、球数制限との整合性が取れた
-
暑さのピークを避けやすくなり、熱中症リスクが軽減された
デメリット
-
深夜試合は選手だけでなく応援団や球場スタッフにも大きな負担
-
地方校ほど宿泊費・移動費がかさみ、遠征コストが増加
-
「いっそドーム開催にすべき」「7回制に短縮した方が合理的」といった根本的な議論も再燃
「朝夕2部制」と「時間制限」を組み合わせた今回の仕組みは、酷暑対策と公平性を両立させるための挑戦的な試みです。
大会側は空白日を用意して日程崩壊を防ぎつつ、選手たちは乱れがちな生活リズムや体調と戦う――この両者のせめぎ合いが、2025年夏の甲子園をこれまで以上に緊張感のある舞台へと変えています。
今後も運営側は改善を重ね、より安全で魅力ある大会づくりを進めていく必要があるでしょう。
再開手順と当日の流れ

今大会から採用された「継続試合」は、試合が途中で中断された場合、翌日の第1試合枠で再開されることが原則となっています。
再開試合では、午前7時半ごろからウォームアップが始まるケースが多く、選手たちは通常よりも早い時間に準備を整える必要があります。
観戦を予定している方は、前夜に甲子園公式サイトや球場のSNSで再開時刻を確認することが推奨されています。
1. スケジュール決定までの流れ
試合が中断されると、大会本部は30分以内に公式発表を行い、翌日の再開カードや予定時刻を告知します。
継続試合は最優先で翌朝の第1試合枠に組み込まれ、7:30〜8:00のプレーボールが基本です。
2. 選手の球場入りとウォームアップ
再開試合の日は、両校の選手が午前5時台には宿舎を出発し、6時前には球場に到着します。
ウォームアップも熱中症対策として従来7分だったノックが5分に短縮され、必要に応じて省略される場合もあります。
3. 再開時のルール
試合は中断した場面からそのまま再開されます。
打者や走者の状況、ボールカウント、さらには延長10回以降のタイブレークもすべて引き継がれます。
また投手の球数は通算管理され、1週間500球以内という上限に含まれます。
観戦マナーとスタンド規制

1. 鳴り物応援は22時で終了
夕方の第4試合が22時を過ぎた場合、ドラムやトランペットなどの鳴り物応援は一切禁止となります。
これは選手や周囲への配慮だけでなく、周辺地域への騒音対策としても重要です。
2. 応援スタイルの注意点
イニング間以外の大音量演奏は許可されず、応援団は球場側の指示に従わなければなりません。
また、地方大会を含め、一部球場では日傘や大型フラッグの使用に制限があるため、事前に確認しておくことが大切です。
次なる改善議論:7イニング制とドーム化

1. 7イニング制を巡る動き
高野連は2025年1月に「7イニング制等に関する課題検討会議」を設置し、一般向けのアンケートを実施しました。
医師の間では「熱中症リスク軽減」を理由に賛成する意見が多い一方、「9回こそ高校野球の醍醐味」という反対意見も根強く、意見は拮抗しています。
指導者からも「時間短縮の意義は理解するが、記録や育成面を考慮すべき」と慎重な声が上がっています。
2. 屋内開催という選択肢
もう一つの議論として、猛暑や深夜試合の問題を根本的に解決するため「全国大会をドームで開催する」という案も浮上しています。
ただし、甲子園が持つ歴史的価値やアクセス面を重視する声が強く、現段階では実現には慎重な姿勢がとられています。
まとめ
「継続試合」を軸に進められた2025年夏の甲子園は、球児の安全と公平性を最優先にしつつも、22時以降の応援規制や早朝再開による負担といった新たな課題も浮き彫りにしました。
今後は7イニング制の導入や開催形態の見直しなど、「選手ファースト」を具体化するためのさらなる議論が求められます。
この夏の経験と検証が、高校野球の未来を形作る大きな一歩となるでしょう。