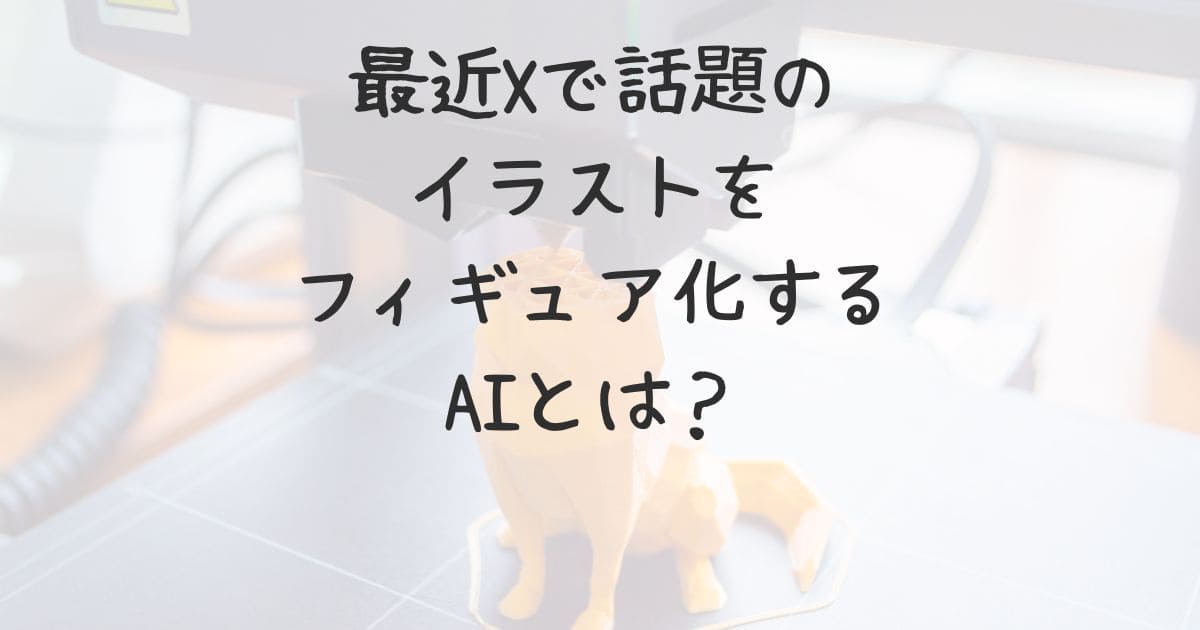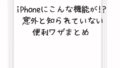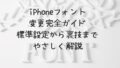話題になっている現象とは?
X(旧Twitter)では最近、イラストがまるで”箱入りフィギュア”になったような画像が次々に投稿され、注目を集めています。
キャラクターの全身がプラスチック製フィギュア風に立体化され、さらに実際の商品パッケージのような箱に収まっている様子が描かれているのが特徴です。
一見すると、どこかのメーカーが本当に販売しているように見えるほどリアルな画像ばかりです。
この現象の裏には、最新の画像生成AIと、ユーザーの間で共有されているテンプレートやプロンプトの工夫があります。
この記事では、どのツールを使えばこのような画像が作れるのか、具体的な手順や注意点も含めてわかりやすく解説します。
フィギュア風画像を作れる主要AIサービス

Google Gemini + Flash Image モデル
現在最も注目を集めているのが、Googleの生成AI「Gemini(旧Bard)」の画像生成モデル “Flash Image 2.5” を活用した方法です。
このモデルは、単なる画像生成にとどまらず、キャラクターイラストを立体的なフィギュア風に変換するのに特化しており、質感やライティング、角度までリアルに再現してくれます。
GeminiのAI Studioを使えば、あらかじめ用意したイラストをアップロードし、簡単なプロンプトを入力するだけで、本物のフィギュアのような見た目を持つ画像が自動生成されるため、初心者でも手軽に使いこなせる点が人気の理由となっています。
また、X(旧Twitter)などでよく見かける「Nano Banana」や「Banana Figure」といったテンプレートも、こうした画像生成の流行に拍車をかけています。
これらは有志が作成・共有した非公式テンプレートであり、Geminiの出力精度を高めるための指示文が工夫されています。
現在は一般公開されていないケースが多いため、自分で試行錯誤してオリジナルのプロンプトを調整したり、SNS上で共有されている事例を参考にしたりすることで、自分だけのフィギュア風出力を追求するユーザーも増えています。
Meshy AI
Meshyは、イラストや2D画像をもとにしてリアルな3Dメッシュモデルを生成できるWebベースのAIツールです。
GLBやOBJといった3Dデータ形式に対応しており、生成したデータはそのままBlenderなどの3D編集ソフトで読み込んで調整することが可能です。
特に、実際の3Dプリンタで出力したい人や、ゲーム・VR用途で使いたい人にとっては、Meshyは非常に実用的で柔軟性のあるサービスといえるでしょう。
無料プランでも一定回数までは試すことができ、有料プランではより高解像度かつ高品質な3Dモデルを生成できます。
YouCam Perfect / AI Pro
スマートフォンだけで完結したいユーザーには、「YouCam Perfect」や「YouCam AI Pro」などのアプリも人気です。
これらのアプリには、あらかじめ用意された“箱入りフィギュア風”のテンプレートが搭載されており、画像を読み込むだけでまるで市販フィギュアのパッケージ写真のような仕上がりになります。
UIも直感的で操作がしやすいため、画像編集の知識がなくても気軽に楽しめるのが魅力です。
SNSで映える画像を手軽に作成したいというニーズにしっかり応えてくれます。
Microsoft Copilot 3D
Windows環境で作業をする人にとっては、Microsoftの提供するCopilot 3Dも非常に便利な選択肢です。
このツールは、静止画像1枚から3Dモデル(GLB形式)を自動生成する機能を備えており、操作もシンプルで初心者向きです。
出力された3Dデータは、そのまま3Dプリンターで出力することもできますし、ARアプリやゲーム開発にも応用できます。
無料で使える機能も多く、今後のアップデートにも期待が高まっています。
実際の手順(Google Gemini編)

ステップ1:Gemini Studioにアクセス
ステップ2:モデルを「Flash Image」に設定
画面上部、またはサイドバーの「モデル」セレクターから「Flash Image 2.5」またはそれ以降のモデルを選択します。
Flash Imageシリーズは、通常の画像生成モデルよりも速く、かつフィギュアのような立体感や質感を忠実に表現する能力が強化されているのが特徴です。
モデルを間違えるとフィギュア化がうまくいかないこともあるので注意してください。
ステップ3:イラストをアップロード
フィギュア化したいイラストをドラッグ&ドロップでアップロードします。
JPEGかPNG形式が対応しており、特に背景が白や淡い色で、線がくっきりした画像の方がAIが認識しやすく、仕上がりも綺麗になります。
キャラクターが真正面を向いているものや、全身が収まっている構図がおすすめです。
ステップ4:プロンプトを入力
アップロードした画像に対して、AIにどのように加工してほしいかを指定するプロンプト(指示文)を入力します。
以下はXでよく使われている構成の一例です。
このイラストをリアルなフィギュア風に変換してください。
・キャラを全身立体化してください
・プラスチックの質感を強調
・実在のフィギュアのように、透明な箱パッケージに入った状態を描写
・背景は白く、ライティングはスタジオ風
・箱の横に商品名などが記載されたラベルも加えてくださいプロンプトは自分好みにカスタマイズ可能です。「斜めからの構図」「アニメ風仕上げ」「メタリック塗装」など、具体的に伝えることでより精度の高い出力が得られます。
ステップ5:出力画像を保存
数秒から数十秒ほどで画像が生成されます。画面上に表示されたフィギュア風画像は、右上のメニューから「画像として保存」を選ぶことで簡単にダウンロード可能です。
PNG形式の透過画像や、背景付きのJPEGで保存できる場合もあります。
この画像はSNSに投稿するだけでなく、後述する3D変換サービスへ渡してフィギュアを立体出力する素材としても活用できます。
3Dデータにしたい場合は?

イラストから生成したフィギュア風画像を、さらにリアルな3Dデータとして扱いたい場合には、Meshy AIやCopilot 3Dといった3Dモデリング対応のAIツールを活用するのが効果的です。
これらのツールを使うことで、画像1枚から自動的に立体的な3Dモデルを作成でき、3Dプリンターでの出力やCG・VRコンテンツへの転用も可能になります。
以下は、一般的な手順とそのポイントです:
- まず、生成済みのフィギュア風画像(JPEGまたはPNG)をMeshyのWebサイトにアップロードします。アップロード後、AIが画像の輪郭と形状を解析し、立体データを構築してくれます。
- 自動変換処理によって、GLB形式(またはOBJ形式)の3Dデータが出力されます。これらの形式は、さまざまな3Dソフトでの編集や3Dプリント向けサービスに対応しています。
- GLBデータをBlenderなどの3D編集ソフトに読み込んで、細部の形状やスケール、テクスチャの調整を行いましょう。必要に応じて、フィギュアの足場や支柱の追加、不要なポリゴンの削除も行います。
- 最終的にSTL形式で書き出せば、DMM.makeやrinkakなどの3Dプリントサービスに入稿可能です。素材やサイズを選んで正式に出力することで、世界に1つだけのオリジナルフィギュアを手に入れることができます。
このように、AI生成画像は単なる2Dビジュアルにとどまらず、実物として“立体化”できるところまで応用が広がっています。
著作権・利用上の注意点

- 他人のイラストを無断でAI変換し、それをSNSなどに投稿するのは著作権侵害となる可能性が高く、絶対に避けましょう。特に、商用作品やファンアートでも制作者の許可がない場合は違法行為とみなされることがあります。
- 安全にAI画像生成を楽しむには、自分で描いたイラストや、事前にAI変換・公開の許可を得たイラストを使用するのが基本です。イラスト提供者の利用条件が明示されている場合は、その範囲内で使うようにしましょう。
- また、生成された画像や3Dデータを販売したり、グッズ化して収益化したりする場合には、必ず利用しているAIサービスの規約を確認してください。多くのAIプラットフォームでは、商用利用に制限があるか、追加ライセンスが必要となるケースもあります。特に3D出力やECサイトでの展開を考えている方は、事前確認を怠らないことが重要です。
まとめ
Xで流行中の「イラストをフィギュア化するAI画像」は、Google GeminiやMeshy AIといった最新の生成AIツールを使うことで、専門知識がなくても誰でも比較的簡単に作成できます。
特別なソフトをインストールする必要もなく、ブラウザ上で数ステップ操作するだけで、まるで実在するかのようなフィギュア風の画像が手に入る手軽さが、多くのユーザーに支持されている理由の一つです。
特にGeminiのFlash Imageモデルは、従来の画像生成AIよりも飛躍的に精度が高く、フィギュア特有のプラスチックのような質感、立体感、光沢表現、さらには透明なパッケージ越しのディテールなども巧みに再現してくれます。
また、箱入りレイアウトの完成度も高く、プロンプト次第でキャラクターの名前やロゴ、シリーズナンバーなどを自由に追加できる柔軟性も魅力です。
こうした特徴により、単なる“イラストの変換”にとどまらず、まるで市販商品さながらのクオリティを持った作品を作り上げることができます。
まずは、Gemini StudioやMeshyの無料プランから始めて、どのような出力が得られるのかを試してみると良いでしょう。
最初はシンプルなキャラクターイラストからスタートし、慣れてきたら自分のオリジナルキャラや二次創作作品などに応用してみることで、創作の幅が一気に広がるはずです。