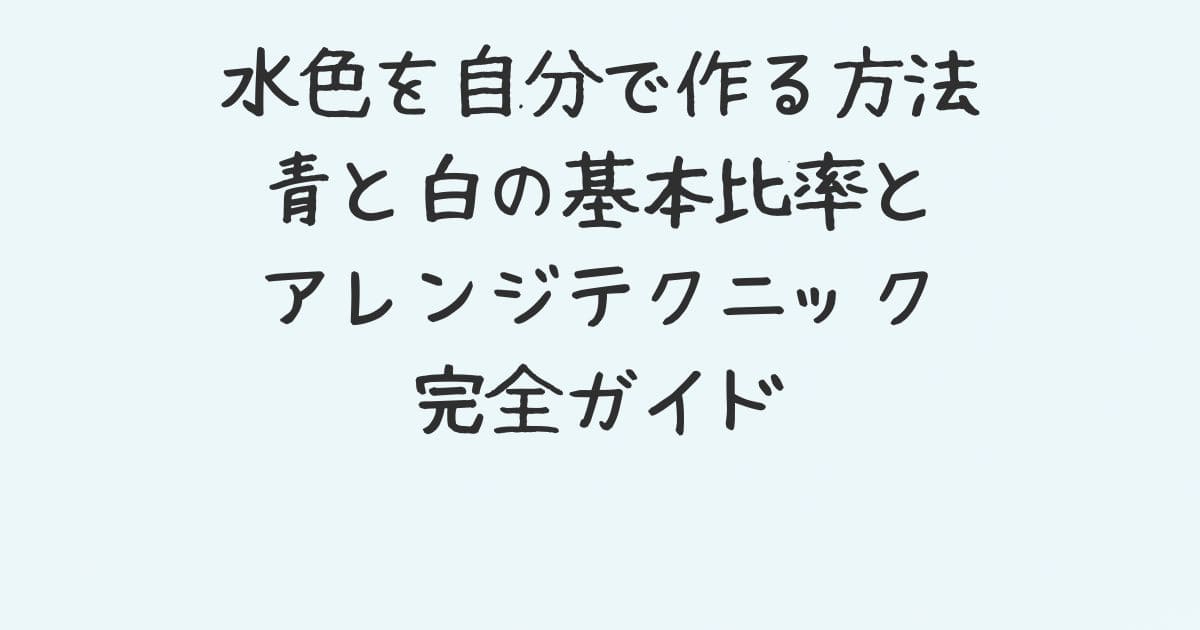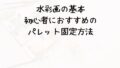最初に知っておきたいこと:水色は「混ぜ方」で印象が変わる
絵の具を混ぜて好きな色を作ることは、楽しい反面、思い通りにならない難しさもあります。
とくに「水色」は、一見シンプルに見えて、微妙な加減によって印象が大きく変わってしまう色です。
この記事では、ただ「青と白を混ぜる」だけでは終わらない、理想の水色を再現するための方法を、わかりやすくご紹介します。
-
基本となる青と白の混ぜ方
-
濃さや明るさの調整方法
-
透明感のある塗り方や応用のテクニック
-
空や海、ターコイズ風など、用途別のバリエーション
初心者の方でも失敗しにくく、自分だけの水色を作れるようになるための実践ガイドです。
水色の基本をおさえよう:黄金比は「青1:白1」

まずは青と白を1対1で
水色を作る基本は、とてもシンプル。「青色」と「白色」を1:1の割合で混ぜるだけで、標準的な水色が作れます。
この比率は、初心者にとっても扱いやすく、鮮やかすぎず淡すぎない、ちょうどいいバランスの色になります。
比率ごとの特徴と使い道:
| 比率 | 色の印象 | おすすめの使い方 |
|---|---|---|
| 青1:白2 | かなり淡い水色 | パステル調・優しい背景に最適 |
| 青1:白1 | 標準的な水色 | 空や海の塗りにぴったり |
| 青2:白1 | やや青が強めの水色 | ポスターや強調部分におすすめ |
| 青3:白1 | 深みのある濃い水色 | 夕方の空や夜の風景に活躍 |
色を混ぜるときは、いきなり大量に混ぜず、少しずつ加えて調整するのがポイントです。
たとえば、最初に白を少なめに加えておいて、あとから少しずつ足すと、自分好みの水色に調整しやすくなります。
見た目で確認できる「色見本」があると便利
パレット上で比率ごとの色を並べて比較できる「色見本」や「カラースウォッチ」を作っておくと、調整しやすく、再現性も高まります。作品ごとに記録しておくのもおすすめです。
青の種類を変えるだけで水色の印象ががらりと変わる

実は、同じ青と白の比率でも、使う「青の種類」によって、水色の印象は大きく変わります。
代表的な青色の絵の具と水色の仕上がり
-
群青(ウルトラマリン系)
→ 少し紫がかった落ち着きのある水色。深みと品のある雰囲気に。 -
コバルトブルー
→ 明るく爽やかな発色が特徴。夏の青空を思わせる軽やかな水色に。 -
プルシアンブルー/藍色
→ 深みと渋さのある青。海のような静けさを表現したいときに最適。
青の種類別・混色イメージ
| 青の種類 | 混ぜ方の例と仕上がりの印象 |
|---|---|
| 群青 | 青5:赤1などで微妙に紫みを足すと深みのある水色に |
| 藍色(深青) | 白を少なめにして濃く調整。静けさや落ち着き感が出せる |
| コバルトブルー | 白を多めにすると明るさが際立ち、透明感のある水色に |
このように、使う青の絵の具を変えるだけで、同じ比率でも全く異なる雰囲気の水色が生まれます。用途や描きたい世界観に合わせて、絵の具選びから工夫してみてください。
水色の濃さや透明感を自由にコントロールするテクニック

白・青・黄色を使った微調整のコツ
水色の印象は、混ぜる色の割合によって大きく変わります。
目的に合わせて、以下のように調整してみましょう。
-
白を多く加えると…
→ 優しく柔らかなパステル調に仕上がります。水彩の背景や、子ども向けの作品にぴったりです。 -
青を多めにすると…
→ 深みのある濃い水色になります。夕暮れの空や、落ち着いた海の色を表現したいときにおすすめ。 -
黄色をほんの少し加えると…
→ エメラルドグリーンやターコイズのようなニュアンスをプラスできます。ただし入れすぎると緑っぽくなってしまうので、少量ずつ様子を見ながら調整しましょう。
とくに黄色を加えるときは、青+白+黄色の順で、極少量からスタートするのが安全です。
小さく試してから全体に広げることで、失敗を防げます。
水彩ならではの透明感を引き出す方法
水色に透明感を持たせるには、「水分量の調整」がポイントです。
特に水彩や水性アクリルでは、水の使い方次第で仕上がりが大きく変わります。
-
水を多く含ませて薄く塗る
→ 透明感のある淡い色になります。ただし、紙が波打ちやすくなるので、重ね塗りする前にしっかり乾かすことが大切です。 -
余分な水分はこまめに吸い取る
→ 染みやムラを防ぐために、乾いた布やティッシュで軽く押さえると、色が落ち着いてきれいに整います。 -
水ではなく「透明メディウム(ジェルタイプ)」を使う方法も
→ ペンキ系やアクリル絵具には、専用の透明メディウムを使うと、均一でにじみにくく、クリアな発色が出せます。特にムラを抑えたいときに便利です。
よくある失敗と、その解決策

失敗①:色ムラやにじみができてしまう
主な原因
水分と絵具の量が合っていないまま塗り始めてしまうことが多いです。
対処法
-
筆を使う前に、ティッシュで水分量を整える
-
面積が広い場合は、あらかじめ混色した色を十分に用意しておく
-
複数回に分けて塗る場合は、乾かしながら区切って作業しましょう
-
染み込んでしまった部分は、布で軽く吸い取ると整います
失敗②:色が濁ってしまった(いわゆる“泥水色”)
主な原因
いろいろな色を混ぜすぎたり、乾かないうちに重ね塗りをしたことが原因です。
対処法
-
層ごとにしっかり乾かしてから重ねるのが基本です
-
特に補色(例:青とオレンジ)の重ね塗りは避けるように注意
-
すでに濁ってしまった部分は、水で拭き取る、または白絵具で塗り直すことで部分的に修正できます
失敗③:紙が波打ってしまい、塗りにくくなる
主な原因
水分が多すぎる状態で塗ったり、乾く前に複数の層を重ねてしまうことです。
対処法
-
厚手の水彩紙(140lb以上)を使うと反りにくくなります
-
作業前に紙全体を軽く湿らせておいて、乾かすことで伸ばしておくと安定しやすいです
-
層を重ねる前には必ず乾燥を確認することを習慣にしましょう
応用編:色を修正する高度なテクニック

リフティング(色を戻す方法)
-
塗ったばかりのときは:すぐにティッシュで軽く吸い取ることで、色を薄くできます
-
乾いた後でも:筆先に水を含ませ、軽くこすりながらティッシュで拭くと色が戻せます
※ただし、薄い紙やコットン紙以外では表面が傷つくこともあるので、慎重に行いましょう
グワッシュ(不透明水彩)での上塗り修正
透明水彩の上から白や淡いグワッシュ(ガッシュ)絵具を重ね塗りすることで、色ムラや濃すぎた部分を目立たなくすることができます。
ただし、透明感は損なわれてしまうため、仕上がりの雰囲気を考慮しながら使いましょう。
最終手段:塗り直すという選択
どうしてもうまくいかないときは、無理に修正せず、最初から描き直すこともひとつの方法です。下絵を複数描いておいて試しながら感覚をつかみ、本番に挑むと安心です。
-
白・青・黄色・水の配分を調整するだけで、さまざまな水色が表現可能
-
水彩や水性絵具は「水分管理」がとても重要
-
失敗しても、リフティングやガッシュ上塗りでリカバリーができる
水色の濃淡や透明感を思い通りにコントロールできるようになれば、絵の表現力がぐっと広がります。ぜひ、あなたらしい水色づくりにチャレンジしてみてくださいね。
シーン別に使い分ける水色|空・海・ターコイズの色作りテクニック

空を描くときの水色
水色を使った表現の中でも「空」を描くのは基本中の基本です。
まずは、青と白を1:1の割合で混ぜるところから始めましょう。
この比率でできる水色は、自然で穏やかな晴天の空にぴったりのトーンになります。
より明るく爽やかな空を描きたい場合は、白をやや多めに加えるのがおすすめ。
さらに、水で薄めた色をグラデーションになるように何層かに分けて重ね塗りすれば、空の奥行きや透明感も表現できます。
重ねる際は、前の層が完全に乾いてから次の色をのせることで、澄んだ仕上がりに近づけます。
海をイメージした深みのある水色
海の色を表現するなら、基本比率は青2~3:白1。青を多めにすることで、深みや落ち着きのある水色になります。
とくに、ウルトラマリンブルーやプルシアンブルーなどをベースに使うと、海らしい奥深い色合いを再現しやすくなります。
波の影や水の揺らぎも、濃淡の変化で表現できるので、複数の比率で作った水色を組み合わせるのも効果的です。
もし透明感のあるエメラルド寄りの海を描きたいときは、少量の緑+白を加えて、ターコイズブルー風に仕上げてみましょう。
ターコイズブルーの作り方
自然の清涼感やリゾートのような雰囲気を表現したいときにぴったりなのが、ターコイズブルーです。
基本の作り方は、青と緑を3:1の比率で混ぜること。これだけでも鮮やかなターコイズができますが、柔らかな印象にしたいときは、ここに白を加えてトーンを調整します。
たとえば、青2:緑1:白2の割合にすると、淡くミルキーな雰囲気が出せます。川のせせらぎや涼しげな風景、雑貨・インテリアなどにもよく合う色味です。