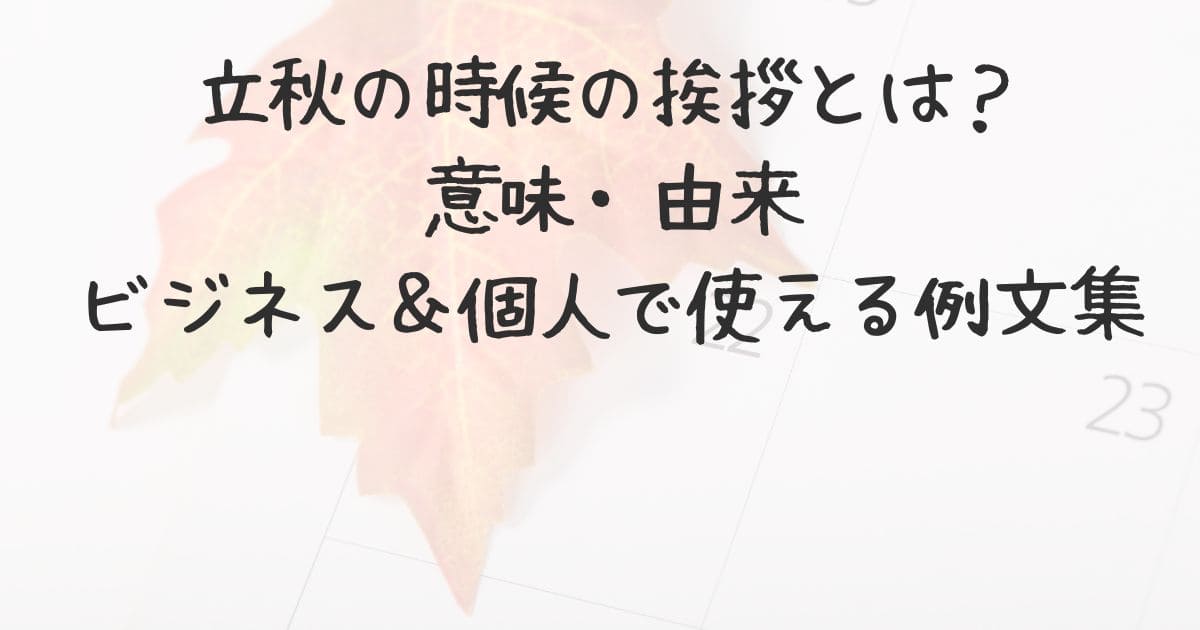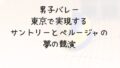立秋とは?意味・時期・季節感をわかりやすく解説
立秋(りっしゅう)は、二十四節気のひとつで、暦の上では秋の始まりを告げる日です。
毎年8月7日ごろに訪れますが、実際の気候はまだまだ厳しい暑さが続き、真夏を思わせるような日差しや蝉の鳴き声も響いています。
それでも、ふとした瞬間に朝夕の風が心地よく感じられたり、空の色が少しだけ柔らかくなったりと、秋の気配を感じられるようになる大切な時期です。
立秋は四季の移ろいを感じる節目でもあり、古くから人々の生活や行事に深く結びついてきました。
2025年の立秋は8月7日(水)で、この日から暦の上では秋に入ります。
立秋と残暑の関係

「立秋」を過ぎると、暑中見舞いから残暑見舞いへ切り替えるのが日本の手紙文化におけるマナーとされています。
これは、暦の上で秋に入ったことを示すためですが、実際の気候はまだ高温の日が多く、体調管理にも気を配る必要があります。
そのため、この時期の挨拶文には「暑さが続く中でのお気遣い」や「お体をご自愛ください」といった、相手を思いやる一言を添えると、より温かみと誠意が伝わる文章になります。
「立秋の候」の意味と由来
「候(こう)」とは、季節や天候を表す漢語で、古くから日本語の中に取り入れられてきた表現です。
本来は「こう」と読み、自然や季節の移ろいを端的に伝える役割を持っています。
「立秋の候」という場合は、「秋が始まるこの時期にあたり」という意味になり、暦の上の変わり目を丁寧に示す言葉として使われます。
日本の手紙文化では、文章の冒頭にこうした時候の挨拶を添えることで、単なる用件伝達にとどまらず、季節の空気感や相手を思いやる心情を伝えることができます。
また、こうした挨拶は相手との距離感を柔らかくし、読み手に温かみを感じさせる効果もあり、古くからビジネスや個人の手紙の中で重宝されてきました。
ビジネス文書での「立秋の候」の使い方と例文

例文①:取引先への挨拶文
拝啓 立秋の候、貴社におかれましては益々ご清栄のことと心よりお喜び申し上げます。日頃より格別のご高配を賜り、心より感謝申し上げますとともに、立秋を迎え少しずつ秋の気配が漂う中、皆様のご健勝とご発展をお祈りいたします。
例文②:お礼状に添える挨拶
拝啓 立秋の候、平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。日頃から温かいお心遣いを頂戴し、心より御礼申し上げます。まだ暑さが続く折ではございますが、どうぞお体には十分お気をつけくださいませ。
例文③:残暑見舞いとして活用
拝啓 立秋の候、暑さ厳しき折、皆様におかれましてはお変わりなくお過ごしでしょうか。朝夕には少し涼しさを感じるようになりましたが、日中はなお残暑が厳しく、体調管理にもご留意いただければと存じます。
ビジネス文書では、相手の立場や状況を考え、簡潔で丁寧な言葉を選びましょう。
個人の手紙で使える「立秋の候」の挨拶例
例文①:友人への近況報告
立秋の候、まだまだ真夏のような強い日差しと蒸し暑さが続いていますが、お変わりなくお元気でお過ごしでしょうか。日中は汗ばむ陽気でも、夕暮れ時にはどこか涼やかな風が感じられ、少しずつ秋の訪れが近づいていることを実感いたします。
例文②:お世話になった方へのお礼
立秋の候、日中の暑さは依然として残っておりますが、朝夕の風は心地よく、季節の移ろいを感じられるようになってまいりました。お変わりなくお過ごしのご様子を嬉しく存じます。これからも暑さが続くと思われますので、どうぞお体には十分ご自愛くださいませ。
個人宛の手紙では、堅苦しくなりすぎず、身近な季節の話題や相手を思う一言を添えることで、文章全体がぐっと親しみやすく、温かみのある印象になります。
立秋を使った他の季節の挨拶文例

- 「初秋の候」:より秋らしさを出したいときに用いられる表現で、立秋を過ぎてから秋の気配が濃くなってきた時期にぴったりです。季節の移ろいをより鮮やかに伝えることができ、文章全体に落ち着いた雰囲気を添えることができます。
- 「新涼の候」:涼しさを感じ始めた時期に使う言葉で、朝夕の風が心地よくなり、日中との温度差が感じられる頃に最適です。相手に爽やかな季節感を届ける効果があります。
これらの表現は、季節の花や行事(例:コスモス、十五夜、お月見)と組み合わせることで、さらにオリジナリティのある挨拶文に仕上がります。
例えば「初秋の候、庭先の萩が咲き始め…」や「新涼の候、夕暮れに虫の声が響く頃…」など、具体的な情景を添えることで読み手の心に残る文章になります。
「立秋の候」の代わりに使える言葉一覧

- 初秋の候:秋らしさを表現したいとき
- 新涼の候:涼しさや爽やかさを伝えたいとき
- 晩夏の候:夏の終わりを感じさせるとき
それぞれ微妙にニュアンスが異なるため、送る相手や時期に合わせて選びましょう。
立秋の候を英語で表現するには?

英語では「In the early days of autumn」や「With the beginning of autumn」などが近い表現としてよく使われます。
また、文脈によっては「At the start of autumn」や「As autumn begins」といった表現も適しています。
特に海外の方に送る場合は、日本の二十四節気や暦上の季節の変化が馴染みのないことも多いため、秋の始まりをシンプルな言葉で補足説明すると伝わりやすくなります。
例えば、「According to the traditional Japanese calendar, autumn begins around early August.」のように背景を一文加えると、文化的な意味合いも共有できます。
メールで「立秋の候」を使うときの注意点

メールではあまり長い挨拶文を入れると読みにくくなります。
短く、わかりやすい文章にまとめることが大切です。
特にスマートフォンなど小さい画面で読む場合は、冒頭の挨拶を2〜3行以内に収めると読み手の負担が軽くなり、好印象を与えることができます。
メール文例(ビジネス)
立秋の候、貴社ますますご発展のこととお喜び申し上げます。朝夕の風に少しずつ秋の気配が感じられるとはいえ、日中はまだ暑さが厳しい時期ですので、皆様におかれましてはどうぞご自愛のうえお過ごしくださいませ。
メール文例(個人)
立秋の候、お変わりなくお過ごしですか。日差しは強くとも、虫の声や空の色にほんの少し秋らしさが漂い始めましたね。体調を崩しやすい季節の変わり目ですので、お元気でお過ごしください。
間違いやすい「立秋」関連の表現
- 立秋以降は「暑中見舞い」ではなく「残暑見舞い」を使う
- 季節感が合わない言葉(例:真冬を連想させる表現や時期外れの行事)は避ける
立秋にまつわる豆知識

立秋の頃は七十二候で「涼風至(すずかぜいたる)」「寒蝉鳴(ひぐらしなく)」「蒙霧升降(ふかききりまとう)」といった情緒あふれる呼び名があり、それぞれが自然界の変化や季節の移ろいを細やかに表現しています。
「涼風至」は立秋を迎えて吹き始める涼やかな風を、「寒蝉鳴」は夏の終わりを告げるヒグラシの鳴き声を、「蒙霧升降」は朝晩の霧が濃く立ち込める様子を指します。
これらの言葉からは、昔の人々が五感を通じて季節の変化を感じ取り、その情景を大切に記録してきたことがうかがえます。
古くから人々はこうした自然の移ろいを生活や暦に反映させ、詩や絵画、挨拶文などさまざまな形で表現してきました。
立秋の時期に合わせたい話題・季節ネタ集

- 花:朝顔、萩、コスモスなど、夏から秋へと咲き継ぐ花々
- 食べ物:スイカ、梨、ぶどうといった旬の味覚や、秋を先取りする栗やサツマイモ
- 行事:お盆、花火大会、盆踊りなど、地域ごとの季節行事や風物詩
立秋に合わせて使える他の時候の挨拶早見表(8月〜9月)

- 8月上旬:立秋の候、初秋の候
- 8月中旬〜下旬:残暑の候、新涼の候
- 9月初旬:初秋の候、秋涼の候
まとめ|言葉に季節を込めて、心に残る挨拶を
「立秋の候」は、単なる形式的な決まり文句ではなく、季節の微妙な移ろいを感じ取りながら、相手の健康や日々の暮らしを思いやる、日本ならではの奥深い表現です。
この言葉には、暑さが残る中にも秋の訪れを喜ぶ気持ちや、季節の変わり目に寄せる優しい気遣いが込められています。
相手や場面に合わせて言葉を選び分ければ、手紙やメールがぐっと温かみのあるものになり、読む人の心に長く残る印象を与えることができます。
さらに、ちょっとした情景描写や季節の話題を添えることで、やり取りがより豊かで親密なものになり、距離を縮めるきっかけにもなるでしょう。