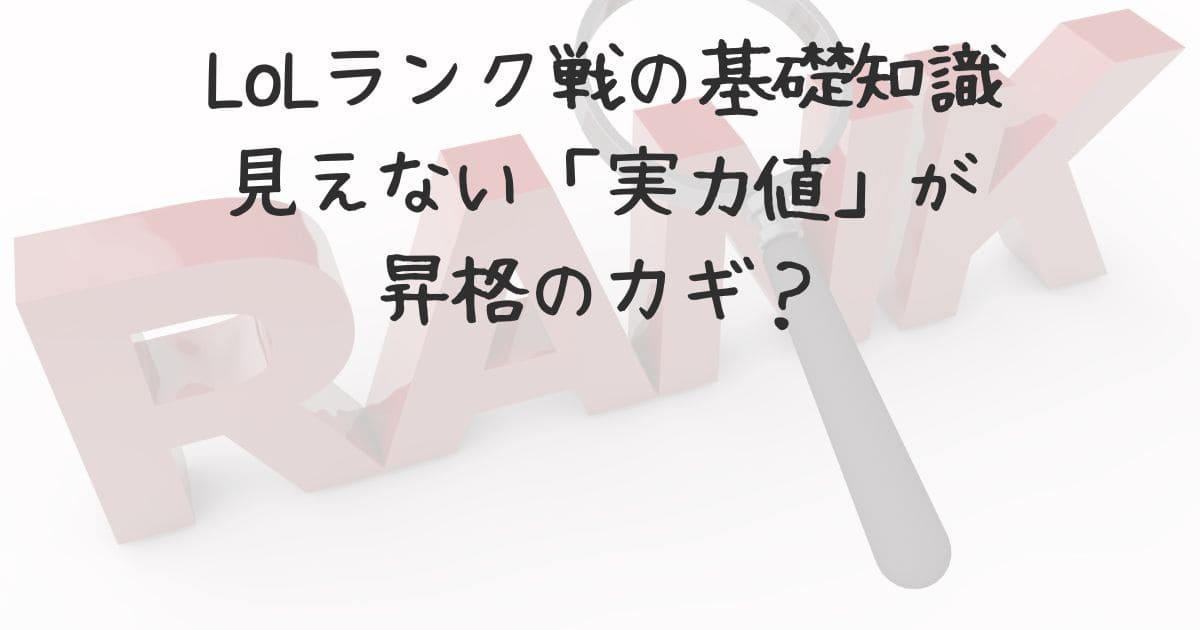League of Legends(LoL)の魅力の一つに「ランク戦」があります。
自分の腕前が数値として評価され、ティアやディビジョンという形ではっきりと可視化されるこのシステムは、多くのプレイヤーにとってやりがいのある挑戦です。
一方で、「なぜ勝っているのにランクが上がらないの?」「どうしてあの人は簡単にゴールドに行けるの?」といった疑問や悩みを抱く方も少なくないはず。
今回は、そんなLoLのランクマッチについて、仕組みの裏側やティアの階層、昇格と降格のルールまで、初心者にも分かりやすく整理してご紹介します。
実は見えない?LoLを支える“MMR”の正体

ランク戦と聞くと、「アイアン」「シルバー」「ゴールド」などのティアや「IV〜I」のディビジョンが真っ先に思い浮かぶかもしれません。
でも、その舞台裏では、もう一つの重要な指標がプレイヤーの評価を左右しています。
それが「MMR(Matchmaking Rating)」と呼ばれる内部レートです。
MMRは、プレイヤーの実力を数値化したものですが、ゲーム内では表示されません。
しかし、このMMRが対戦相手の選定や、勝敗によるLP(リーグポイント)の増減に大きく関わっています。
たとえば、現在のランクに対してMMRが高めだと、勝利時に得られるLPが多く、逆に負けても減るLPは少なめ。
つまり「あなたは今のランクより上のレベルですよ」とシステムが評価してくれている状態です。
反対に、MMRがランクよりも低い場合は、勝ってもLPはわずか、負けると大きくマイナスになる…という厳しい展開に。
悔しい思いをするかもしれませんが、これは実力とランクの差を調整しようとする仕組みなのです。
ランクを動かす“LP”の仕組みとは?

LP(リーグポイント)は、ランク戦の進捗を示すメイン指標です。試合に勝てばLPが増え、負ければ減少します。
ポイントの変動は、マッチングした相手の強さや自身のMMRの状態など、さまざまな要素によって左右されます。
そしてランク戦に参加する際に最初に行うのが、「プレースメントマッチ」と呼ばれる数試合の振り分け戦です。
このプレースメントでは、全勝すればより高いランクから始まることが可能ですが、たとえ勝率が五分でもプレイ内容が良ければ、比較的上のディビジョンからスタートできることもあります。
私自身、初めてのプレースメントマッチは非常に緊張しましたが、ここでの頑張りがその後のランクアップに向けた大きな第一歩となりました。
ティアとディビジョンの構造を把握しよう

LoLのランクは、下位から順に「アイアン」「ブロンズ」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」「エメラルド」「ダイヤモンド」「マスター」「グランドマスター」「チャレンジャー」の10ティアで構成されています。
このうちアイアンからダイヤモンドまでの各ティアには、さらに「IV(4)」から「I(1)」までのディビジョンが設けられており、「I」がそのティア内で最も高い位置づけになります。
たとえば、シルバーIIIにいる状態でLPが100まで貯まると、次のディビジョン(シルバーII)への昇格戦が始まります。この「プロモーションシリーズ」は3戦中2勝すれば突破可能。
そしてティア最上位(シルバーIなど)で再度LPが100になると、次のティア(ゴールド)へと自動昇格します。
もちろん、負け続けてLPがゼロになると降格もありえます。とくに連敗が続けばディビジョンだけでなくティアごと落ちてしまうこともあるので、安定したパフォーマンスが求められます。
ダイヤモンド以上では「維持」もまた実力の証明

ダイヤモンドIVを超えると、さらに一段階上のルールが適用されるようになります。それが「ランク低下(Decay)」という仕組みです。
これは、一定期間ランク戦をプレイしていない高ランクプレイヤーのLPを自動的に減少させ、活動がない状態でのランク維持を防ぐものです。
つまり、ダイヤモンド以上のティアにとどまり続けるには、実力だけでなく、継続してプレイし続ける情熱と努力も必要になるのです。
この制度があることで、最上位のランク帯には、常にアクティブかつ実力あるプレイヤーが揃う環境が保たれています。
以上が、LoLのランクシステムの基本的な仕組みと昇格・降格のポイントです。
自分のランクに伸び悩んでいる方も、これらのルールを理解することで、次の一手が見えてくるかもしれません。
さらに上位を目指すために必要な心構えやスキルアップのコツなども、別記事でご紹介していますので、ぜひそちらもあわせてご覧ください。
ソロ?フレックス?LoLランク戦のタイプ別プレイスタイルガイド

League of Legendsのランクマッチには、プレイヤーの目的や性格に応じて選べる2つのメインモードがあります。
それが「ソロ/デュオキュー」と「フレックスキュー」です。
どちらを選ぶかでゲームの雰囲気も、求められる立ち回りも大きく変わります。
自分に合ったランク戦の形式を理解することが、上達への近道になります。
実力勝負の舞台「ソロ/デュオキュー」
ソロ/デュオキューは、自分のスキルや判断力がそのまま勝敗に直結する真剣勝負のフィールド。
一人で参戦することも、フレンドと2人で組むこともできますが、基本的には知らないプレイヤーたちとチームを組み、毎試合ごとに異なる味方・相手と戦うことになります。
このキューでは、戦略的な判断力(マクロ)と操作の正確さ(ミクロ)の両方が問われます。
そして成績は個人ごとに評価されるため、まさに「自分の力だけでランクを押し上げていく」場といえるでしょう。
なお、グランドマスター以上の上位帯になると、2人での参加すら許されず、完全ソロでのプレイが求められます。頂点を目指すためには、自分一人の実力で勝ち抜くしかないのです。
チーム戦術を楽しむ「フレックスキュー」
もう一方の「フレックスキュー」は、仲間との連携や作戦を重視するプレイに最適なモードです。
1〜5人までのパーティーで参加でき、戦略的なチーム構成や集団戦の練習にも向いています。ただし、4人でのグループだけは参加できないという特殊な制限があります。
このモードは、イベント「Clash」の練習や、チームプレイの精度を高めたい方にぴったり。
試したい構成や動きがあるとき、気心の知れた仲間と試合に挑むのに最適です。
また、ティア(ランク)の違いによる参加制限も、ソロ/デュオに比べてやや緩やか。
プラチナ以下なら、フレンドとティアを問わずチームを組むことが可能です。
ただし、マスター以上のプレイヤーと一緒にプレイしたい場合は、自身がエメラルド帯にいなければなりません。
回線切れやAFKへの対策はある?
LoLをプレイしていると、突然味方が操作しなくなる「AFK(Away From Keyboard)」や、接続トラブルによる離脱に遭遇することも。
そんな状況では、せっかくのランク戦が台無しになることもありますよね。
このような問題に対応するため、Riot Gamesはさまざまな救済措置を導入しています。
その代表例が「/Remake」機能です。試合開始から3分以内に味方の誰かがAFKになった場合、このコマンドをチャットに入力することで、試合自体を無効化できます。
この機能を使えば、LPやMMRを失うことなく仕切り直しができ、不利な状態で無理に戦うストレスからも解放されます。
また、意図的に試合を放棄したり、繰り返しAFKを繰り返すプレイヤーには、ペナルティが科される仕組みも整えられています。
健全なランク戦環境を守るため、開発側も継続的に対策を講じているのです。
勝率を上げたいなら「習慣」を変えよう
LoLで勝ち続けるためには、スキルや知識だけでなく、日頃の“意識の持ち方”も大切です。
その中でも特に重要なのが、ミニマップを見る習慣です。
たとえば、ミニオンを1体倒すたびに地図を確認するクセをつけるだけでも、敵ジャングラーの動きを予測しやすくなり、無駄なデスを減らすことができます。
また、味方のピン(合図)にしっかり反応することで、チームの連携も向上します。
さらに、初心者のうちは操作が簡単なチャンピオンを選ぶのがおすすめです。
耐久力のあるジャガーノート系のようなキャラなら、多少のミスがあっても立て直しやすく、基本的な動きに集中できます。
私もかつては、見た目が魅力的な難易度の高いキャラを選んで敗戦を重ねたことがありました。
しかし、扱いやすいチャンピオンで基礎を固めるようになってから、徐々にプレイが安定し、勝てるようになったのです。
冷静さを保つ力も、立派なスキル
LoLのランク戦では、技術だけでなく「心の持ち方」も結果に大きく関わってきます。
特にシルバー〜ゴールド帯では、試合中のちょっとした失敗やミスで、味方同士の空気が悪くなり、勝てるはずの試合が崩れることも珍しくありません。
そんなときこそ、自分の気持ちをコントロールする力が問われます。
ついイライラしたり、味方を責めたくなる場面もあるかもしれません。でも、そこで冷静さを失ってしまうと、自分のプレイまで乱れてしまいます。
どうしても気になる場合は、思い切ってチャットやピンをミュートにしてしまうのも手です。
全員がNPC(コンピュータ)だと思うくらいの意識で、自分の操作にだけ集中することで、意外と良いプレイができたりするものです。
LoLのランクマッチは、自分の成長が目に見えて実感できる素晴らしい場です。
その中で、どのモードを選び、どんな姿勢で臨むかは、すべて自分次第。焦らず、じっくり取り組むことが、着実な上達への近道です。
プラチナに到達するために|勝ち続ける人が実践している考え方とトレーニング法

League of Legendsで上位ランクを目指すなら、ただ試合数をこなすだけでは足りません。
特にゴールド帯を越え、「プラチナ」「エメラルド」といった階層に挑む段階になると、求められるのはプレイヤー個々の技術と考え方の質です。
この記事では、私自身の体験も交えながら、上達するために身につけたい基礎の見直しポイントや、試合後の分析方法、そしてメンタルの整え方まで、実践的なアドバイスをお伝えしていきます。
勝率を安定させるために見直したい「3つの基本」
どんなジャンルのゲームでもそうですが、強くなるためには土台となる基礎力が重要です。
LoLにおいて特に大切なのが、以下の3点です。
-
CS(クリープスコア)の正確さ
-
敵チャンピオンのスキル把握とクールダウン管理
-
視界の確保とワード配置の工夫
この中でも、CSは試合中ずっと継続的に意識できる要素です。
たとえキルに絡めなくても、確実にミニオンを処理してゴールドを稼ぐだけで、装備やパワースパイクに明確な差が生まれます。
また、どこにワードを設置すれば敵の動きを制限できるかを理解しておくと、味方への支援や集団戦での立ち位置も改善され、勝率にもつながっていきます。
操作が複雑なキャラより、使いやすさ重視で挑む
LoLには魅力的でスタイリッシュなチャンピオンがたくさん登場します。
そのため「見た目がかっこいい」という理由で難易度の高いキャラを選んでしまう人も多いのではないでしょうか。
しかし、ランクを安定して上げたいなら、まずは操作がシンプルで扱いやすいチャンピオンに集中することが大切です。
たとえば、ジャガーノート系のように耐久力が高く、スキル構成も分かりやすいキャラは、多少のミスをしても大きな影響が出にくいため、マップを見る余裕や判断力を養いやすい傾向があります。
私自身も、以前はアサシンタイプの高難度キャラに憧れて何度も挑戦しましたが、結果は散々でした。
結局、使いやすいチャンピオンに絞って動きを磨いた方が、実力としてもしっかり身についたと実感しています。
「リプレイを振り返る」習慣が上達のカギ
自分のプレイを振り返ることは、成長のスピードを加速させる最大の武器になります。
勝った試合でも、負けた試合でも、「あのタイミングで引くべきだったかも」「ピンを出していれば味方が対応できたかも」と冷静に考えることで、同じミスを繰り返す確率がぐっと減ります。
特におすすめなのは、試合のリプレイを見直すことです。
最初は自分のミスを見るのがつらいかもしれません。でも、そうやって少しずつ改善点を洗い出していく作業こそが、上位プレイヤーに共通する習慣でもあります。
たとえば、「ここで前に出すぎた」「この時、視界がなかったのに強引だった」といった失敗の理由に気づけた瞬間、自分の“伸びしろ”がハッキリと見えてきます。
メンタルの安定もランクアップには欠かせない
試合中に調子を崩す原因の多くは、精神的な揺れにあります。
連敗が続いて気持ちが沈んだり、味方がミスをして苛立ったり、時には暴言チャットを目にして集中力が乱れてしまう…そんな経験をしたことがある方も多いはず。
こういった場面で重要なのは、「他人を変えようとしない」こと。チャットやピンにストレスを感じるなら、全ミュートにしてしまうのも一つの手です。
試合中のすべてを自分でコントロールするのは難しいですが、「今の自分にできる最善の動きをしよう」と意識するだけでも、驚くほど気持ちが落ち着き、冷静な判断ができるようになります。
私もミュートを活用するようになってから、イライラに流されることが減り、集中力を保てるようになった結果、プレイ内容も安定してきました。
上位帯は“プロレベルの意識”が必要に
プラチナを超えて、ダイヤモンドやマスターの領域に足を踏み入れると、ゲームに対する姿勢そのものが変わってきます。
このクラスのプレイヤーたちは、ただの個人技にとどまらず、チーム全体を見渡しながら動いています。次のような要素が当然のように求められるのです:
-
敵ジャングルへのインベード(奇襲・情報収集)
-
タワーダイブのタイミングと連携
-
ドラゴン・バロンなどオブジェクトのコントロール
こうした判断を、瞬時に、そして的確に行う力がなければ通用しません。まさにLoLを“スポーツ”として捉える感覚が必要になる世界です。
上位ランクに挑戦することは、決して簡単な道ではありません。しかし、一つひとつの基本を積み重ね、冷静さと意識の高さを保ち続けることで、必ず次のステージが見えてきます。
「たくさん試合をしているのに、なかなか上がらない」と感じている方こそ、一度立ち止まって、練習方法やプレイスタイルを見直してみてはいかがでしょうか。
あなたのLoLライフに、新たな突破口が生まれるかもしれません。
ゴールドやプラチナはどのくらいすごい?LoLランク分布で自分の位置を知ろう

「ゴールドに上がれたら強い方なの?」「プラチナってどれくらいの人がいるの?」
League of Legends(LoL)をプレイしていると、そんな素朴な疑問が浮かぶことはありませんか?
本記事では、2025年7月時点の最新データをもとに、ランクごとのプレイヤー割合を詳しくご紹介しながら、自分が今どの位置にいるのか、そして上位ランクがどれほど価値あるものかをわかりやすく解説していきます。
LoLのランク分布は「山の形」
LoLでは、プレイヤーのランク分布がちょうど山のような形をしています。
これは「ベルカーブ(正規分布)」と呼ばれるもので、真ん中のランクに最も多くのプレイヤーが集まり、上位・下位になるほど人数が減っていくというものです。
2025年7月時点のソロランク分布は、次のようになっています:
-
アイアン帯:15%
-
ブロンズ帯:18%
-
シルバー帯:20%(最も多い層)
-
ゴールド帯:19%
-
プラチナ帯:13%
-
エメラルド帯:約9.6%
-
ダイヤモンド帯:約2.5%
-
マスター帯以上:1%未満
- マスター:0.47%
- グランドマスター:0.061%
- チャレンジャー:0.023%
このように、シルバーとゴールドがLoLプレイヤーの“平均的なランク”にあたります。
一方で、ダイヤモンド以上になると全体のごく一部だけが到達できる、まさに上位数パーセントのエリート層といえるでしょう。
偏差値で例えると?ランクのイメージが一気に明確に
ランクの“凄さ”を感覚的に理解するために、学生時代でおなじみの「偏差値」に置き換えてみましょう。
-
シルバーIII付近 → 偏差値50(全体のちょうど真ん中)
-
ゴールド帯 → 偏差値55〜58(少し上)
-
プラチナ帯 → 偏差値60前後(上位13%、優秀層)
-
エメラルド帯 → 偏差値62〜64(上位約8.5%)
-
ダイヤモンド以上 → 偏差値65〜70超(医学部レベルの難関)
このように見てみると、プラチナ以上のランクは単なる“うまい人”ではなく、戦略理解・操作技術・判断力などを兼ね備えた熟練者の領域といえるのです。
「ゴールド」は最初の大きな目標地点

多くのプレイヤーが、最初の明確な目標として目指すのが「ゴールドランク」。
これはランクマッチを始めたばかりの方にとっては、実力を証明する“登竜門”のような存在です。
私自身、始めたばかりの頃は何度も昇格戦に失敗し、「やっとゴールドになれた…!」という達成感を味わったことを今でも覚えています。
かつて俳優のケイン・コスギさんがゴールドに昇格して涙したという話もあるほど。ゴールド到達には、それだけ強い意味と喜びがあるのです。
ランクアップしやすくなった?最近のシステムの変化

ここ数年、ランクシステムに微調整が入り、MMR(マッチメイキングレート)と実際のランクに差がある場合、LP(リーグポイント)の増減に補正がかかるようになっています。
たとえば、自分のMMRがランクよりも高ければ、1勝で+35LP、1敗で-15LPというように、昇格しやすい傾向が見られるのです。
これは、システムが「このプレイヤーはもっと上のランクにいるべきだ」と判断している状態といえます。
私も以前は「プラチナなんて自分には無理だ」と感じていましたが、最近は明らかにLPの上がり方が軽やかで、「もしかしたら行けるかも」と感じることが増えてきました。
環境の変化が、新たな挑戦のチャンスを与えてくれているのです。
まとめ──焦らず、自分のペースで歩み続けよう
LoLのランク戦は、勝った時の喜びと、負けた時の悔しさが入り混じる“成長の場”です。
「何年もかかってやっとゴールドに届いた」
「何千時間プレイしてやっとプラチナになった」
そんな経験をしてきた人たちは、間違いなく“努力し続けた”証人です。時間がかかっても、一歩ずつ積み上げた成長は、決して無駄にはなりません。
これからランクアップを目指すあなたへ、私からのメッセージはひとつです。
「諦めなければ、必ず上達できる」
このガイドが、あなたのサモナーズリフトでの歩みに少しでも力になれたなら幸いです。そして、いつか試合でお会いできることを楽しみにしています。